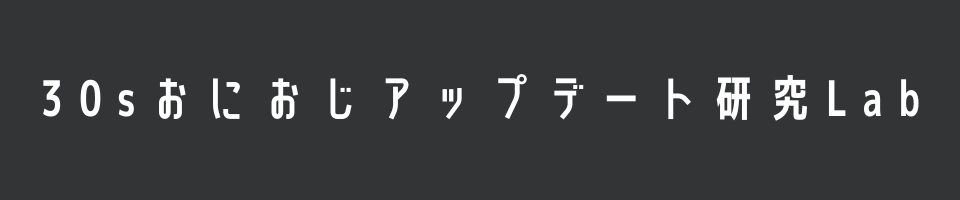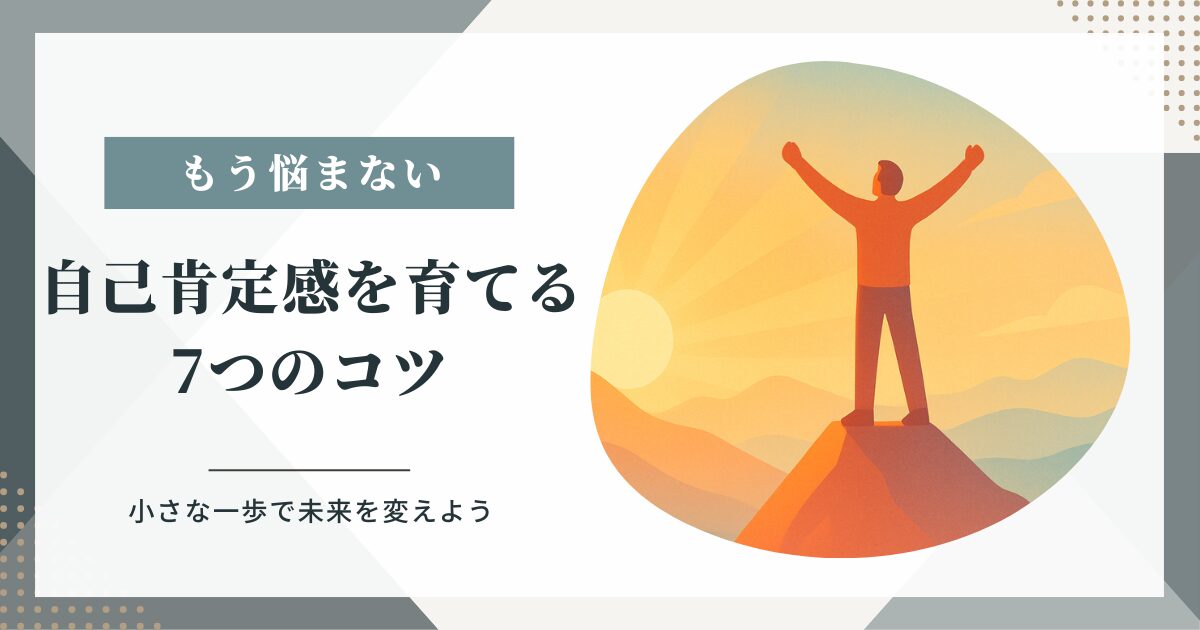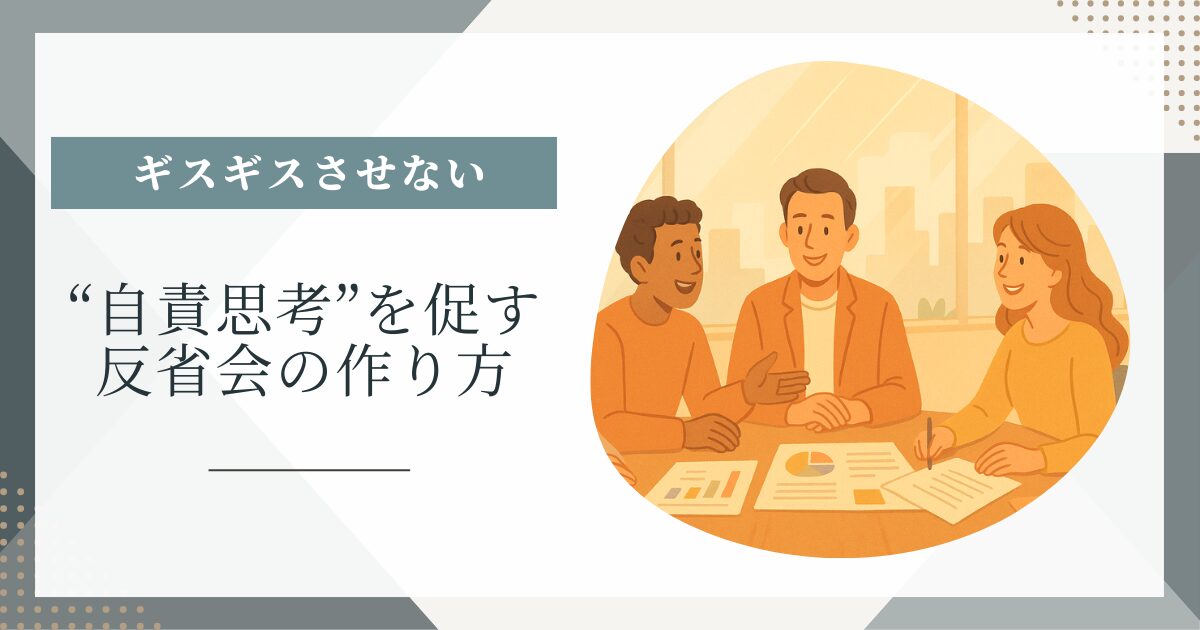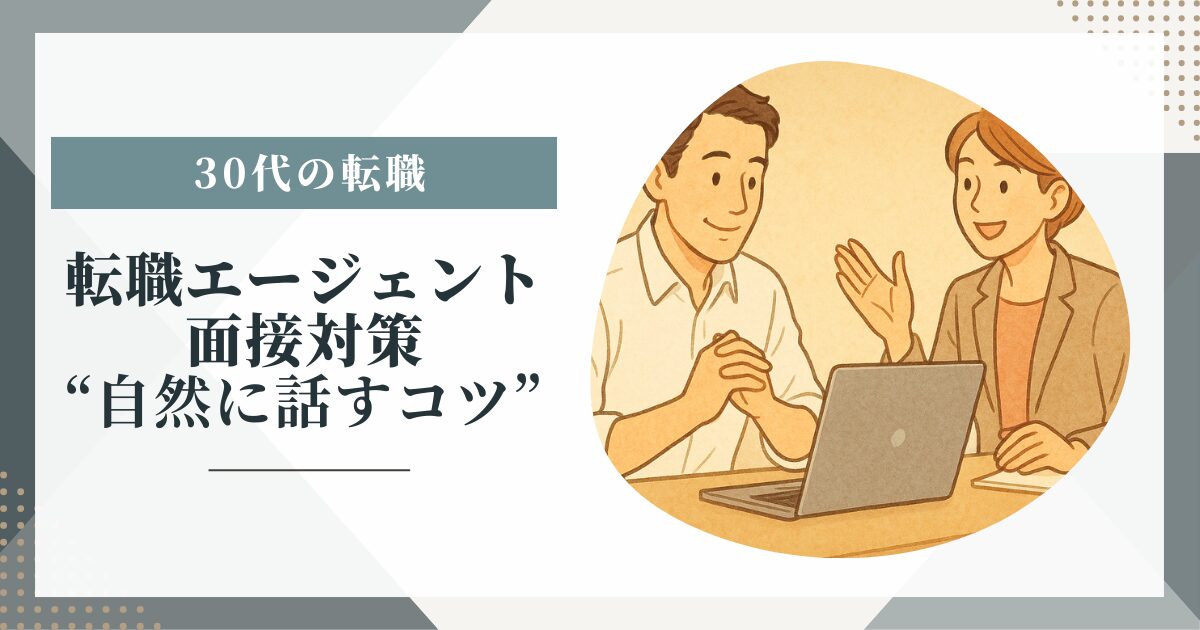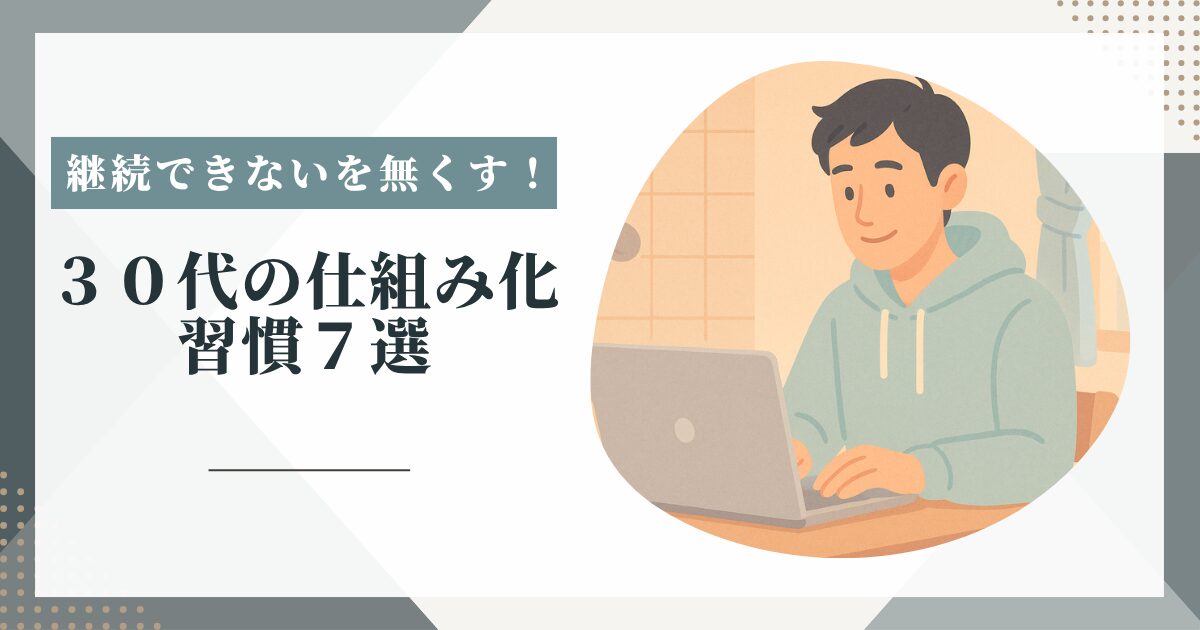『人を動かす』実践記|職場関係が変わった3つの原則
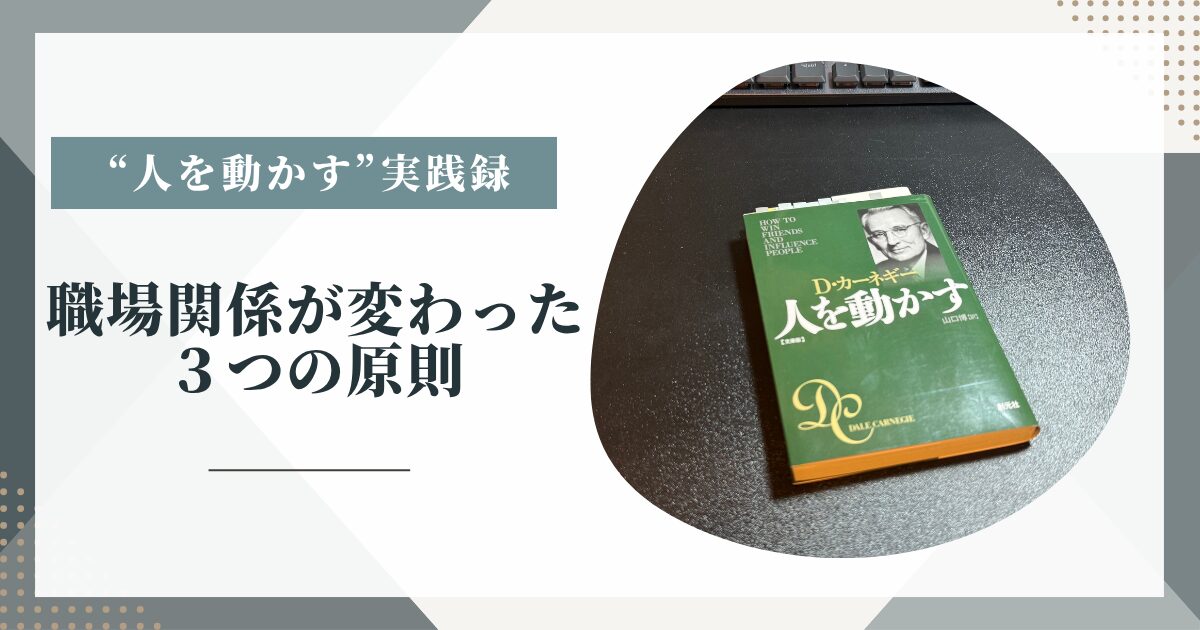
職場のギスギス感、なんとかならない?
「言ったのにやってくれない」
「注意したら反発される」
職場の人間関係って、どれだけ注意していても改善しないことは多々ありますよね。
ぼくも以前、部下の問題行動に悩み、ついには怒鳴ってしまったことがありました…。
そんなときに出会ったのが、D・カーネギー著の『人を動かす』です。
『人を動かす』で学んだ3つの原則
- 誠実な関心を寄せる
- 穏やかに話す
- 人の身になる
これらを意識してから、以前は反発も多かった職場の空気が、少しずつ協力的で温かいものに変わっていきました!
この記事では、原則の実践方法と、うまくいかなかった例も含めて全部お話しします!
読んでもらえれば、怒鳴ったり強く注意しなくても、”人が動いてくれるコミュニケーション”の原則がわかり、明日からの職場コミュニケーションがグッと楽になるはずです!
『人を動かす』との出会いと当時のぼくの状況
3年前、ぼくがメンタル不調で休職をしてしまった直後のことです。
原因は過労にくわえ、特定の上司や部下とのコミュニケーション不全です。
「もっと上手に自分の状況が報告できたら…」
「やってほしいことをきちんと伝えられたら…」
「お願いしたことを正しくやってもらうにはどうしたら…」
休職中でも、働いていたときの後悔が頭からなかなか離れませんでした。
そんなある日、奥さんと立ち寄った本屋さんで、平積みされていた『人を動かす』が偶然目に止まりました。
D・カーネギーが誰なのかも、この本が名著であることもまったく知らなかったのに、
目に止まってタイトルを見た瞬間「これはぼくの願いをかなえてくれる本だ!」と直感しました。
大人になってから2冊目の購入本で、当時の読書習慣はほぼゼロ。
そんなぼくが実際に読んでみると、エピソード・根拠がびっしりで情報量が多く、頭に全然入ってこない…
別の本で読書法を学んだ後、3回目の挑戦でようやく内容を理解することができました!笑
そうして苦戦の末読破した『人を動かす』
その中で「これこそが奥義だ!」と心に残った原則がありました。
それが”誠実な関心を寄せる”です。
実践して効果を感じた3つの原則
① 誠実な関心を寄せる
誠実な関心を寄せる
- 他人に関心を寄せないものは、苦難の人生を歩み、他者に大きな迷惑をかける。
- 相手に関心を寄せない者が、どうして相手に関心を持たれようか。
- こちらが心からの関心を寄せれば、どんなに忙しくとも、聞いてくれ、時間を割いてくれ、協力をしてくれる。
- 友をつくりたいなら、人の理解のために自分の時間と労力を捧げ、没我的な努力を行うこと。
ぼくが最初にこの原則を使った相手は、年上の新入社員。
勤務中にトイレや喫煙での離席が多く、居眠りも頻繁にしてしまう問題児。
さらに、成果物を自主チェックせず「ちゃんとやってます」と嘘までついてしまう…
この時、ぼくは社会人生活で初めて怒鳴ってしまいました。
後にも先にもその一度きりです。
一向に改善されない新入社員でしたが、原則を学んでからはにこう思うようにしました。
「なんでこの人はこんなにも問題行動を繰り返すんだろう。相手のことをきちんと知らないと、ぼくの言葉は伝わらないよな」
そこで、相手を知るため1on1の機会をとって質問をしてみました。
「最近勤務中によく居眠りを繰り返しているけど、体調悪いですか?」
「会社に不満や不安はないですか?」
「一服すると眠気覚めますか?」
という業務中に気になる点から
「休みの日にどうやって気分転換してるんですか?」
「ガンダム好きなんですね!ぼくも大好きなんですけど、どのシリーズをよく見ました?」
といった私的な話題まで広げました。
“こいつを徹底的に知りたい!”という好奇心を無理やり引き出す感じです。
もちろん彼のことは大嫌いでしたが、”友だちになってやる!”くらいな気持ちで挑んでました!
すると彼は、以前パニック障害を患っていたこと、睡眠薬を飲んでも眠れない日があること、喫煙やトイレは眠気覚ましのためだったことを打ち明けてくれました。
そうやって関心をもって接して以降、ぼくに対しては笑顔で接してくれるようになり、ぼくの依頼する仕事だけは真面目にこなすようになってくれました。
(他のメンバーに対する彼の問題態度は最後まで変えられませんでした…)
誠実な関心を寄せると、相手との距離を縮めることができ、協力的な関係を築けるきっかけになります!
これはどんな職場、環境でも使える普遍的な原則です!
② 穏やかに話す
穏やかに話す
- 喧嘩腰でやっつけられて、気持ちよくこちらの思い通りに動いてくれる人間がいるだろうか
- こちらが拳を固めたら、相手も負けじと拳を固めて迎える
- 相手を自分の意見に賛成させたいなら、まずは自分が味方だとわからせることだ
- 親切、友愛、感謝は世の中のどんな怒声よりも容易く人の心を変えることができる。
毎日どんなときでも、穏やかに会話できるよう気をつけるようになりました。
”自分がどう言われたら気持ちよく動けるか”ということを考えたら当然ですよね!
強い口調や命令口調で相手が気持ちよく動くはずがありません。
ぼくは常に口調を意識し、相手と打ち解けられるような言い回しを心がけました。
また、表情にも気を使っています。
誰かと会話をするときには、口角が上がっているかを意識するようになりました。
こういうことを意識しながら会話をしていると、注意や指示も自然と「お願い」という形に変わります。
また、理不尽の会社命令が発生したとき、部下をなだめるときにも有効でした。
「残業したら評価低下に影響がでるのに、営業の受注ミスで残業・休日出勤しないといけない!?ふざけるな!」
と部下が不満を口にしたとき、ぼくは答えや反論を返すのではなく、穏やかに話しながら気持ちに寄り添うことにしました。
「本当に経営陣は、計画を建てずに仕事をとりますよね。この部署は今どんな仕事を抱えているかなんて、こっちがどれだけ進言しても一切耳を貸さないし。経営陣が社内の仕事量をパンクさせて会社の足を引っ張る。これを平気で繰り返して赤字連発させますもんね。」
うんうんと頷きながら話しを聞いているうちに、部下は落ち着いてきて、「本当にそうですよまったく…」と言いいながらも、「取った以上やるしかないですもんね。尻拭いはいっつもうウチらだ」と苦笑しつつ、最終的には真面目に取り組んでくれました。
解決策を示さなくても、穏やかな口調と落ち着いた雰囲気で、ただ共感して耳を貸す。
それだけで、相手は前向きな行動に切り替わることがあります。
これが”穏やかに話す”の力です。
日常の小さなやり取りでも、この原則を意識してみてください!
③ 人の身になる
人の身になる
- 相手は間違っているかもしれないが、相手自身は、自分が間違っているなんて決して思っていない
- 理解することに努めねばならない。賢明な人間は、相手を理解しようと努める
- 人を扱う秘訣は、相手の立場に同情し、それをよく理解することだ
- 自分の意見だけでなく、相手の意見をも尊重するところから、話し合いの道が開ける
この原則を意識し始めてから、問題行動や愚痴が出たときは
「この人に何があったんだ?」と考えるようになりました。
ある部下がミスを連発したときも、理由を聞かずに叱るのではなく、まずは状況を丁寧にヒアリングすることから始めました。
すると仕様決定前に、会社命令で先に製作を開始したことが原因で、追加・変更対応が多発し、出荷後の改造まで発生していたことが分かりました。
つまり、このミスは部下個人の能力不足ではなく、自社の製作計画の杜撰さが引き起こしたものでした。
もし背景を知らずに注意をしていたら、無茶な命令と顧客の間で必死に業務をこなした部下を、さらに追い詰めてしまうところでした。
背景が理解できたことで「再発を防ぐにはどうするか」という建設的な議論につなげて、社内全体の反省会を開くことができました。
相手の立場や背景を知るだけで、対応も結果もまったく変わる
それを実感した出来事です。
うまくいかなかった原則
思いつかせる
- 人は押し付けられるより、自分で思いついた意見の方を遥かに大切にするものである
- 相手に相談をもちかけ、できるだけ意見を取り入れ、それが自分の発案だと相手に思わせえて協力させるのだ
- 賢者は人の上に立たんと欲すれば、人の下に身を置く
相手にしてほしいことがあるとき、相手に「自分で発案したんだ!」と思わせて行動してもらうという原則です。
コーチングの原点とも言えるこの原則ですが、ぼくには話術スキルが足りないためか、ぱっと必要な言葉がまだ出せません。
「どうしたらうまくいくと思うかな?」「これは〇〇と思うんだけど、君はどう考える?」など、相手が主体的に考えてくれるような質問をすることが正しいとのことですが、つい自分の正しいと思ったことを説明してしまします。
その癖がなかなか治せません(_ _;)
今は、まず相手の話を聞くことに集中し、自然と相手の中から答えが出てくるような質問を練習しているところです。
明日からできる簡単ステップ
ここまでの実例をもとにして、あなたが明日から”人を動かす”原則を行うための簡単なステップを紹介します!
- 関心を寄せる質問を1日1つする
「今日は体調どう?」「週末はどう過ごしたの?」など、業務に直接関係ない質問でも1つだけしてみましょう。
人は”自分に興味を持ってくれる人”を好意的に感じます。1日1回でも信頼貯金が増えていきます。 - 口調を”お願い”ベースにする
同じ依頼でも、「〇〇してください」より「〇〇してもらえると助かります」のほうが相手の受け止め方は柔らかくなります。
小さな違いですが、依頼される側からは”協力しよう”という気持ちが生まれます。 - 相手の背景を深堀りして聞く
ミスや不満がでたとき「なんでそう思うの?」と1つだけ聞いてみましょう。
相手の背景を知ることで、本当に改善するべきが本人なのか仕組みなのか環境なのかがはっきりしてきます。
原因が見えてくると、建設的な解決策もとることができます。
この3つはどれも、時間もお金もかからないです!
いずれも習慣として癖にまでなってくれば、1ヶ月もしないうちに、相手からの態度や信頼度に変化が出てくるはずです!
まとめ|原則は“人格”に落とし込むまでがゴール
『人を動かす』で紹介されている原則は、単なる表面的なスキルではありません!
人格にまで落とし込んでこそ、真価を発揮するとぼくは考えています。
ぼくもまだ「誠実に関心を寄せるようにしなくては…!」と意識しないと、つい感情的になってしまうこともあります。
それでも、原則を実践してから、相手との衝突がなくなり、協力関係を築けるようになりました。
あなたもまずは第一歩、目の前の相手に“誠実な関心を寄せる”ところから始めてみてください!
あなたにいい明日がありますように!