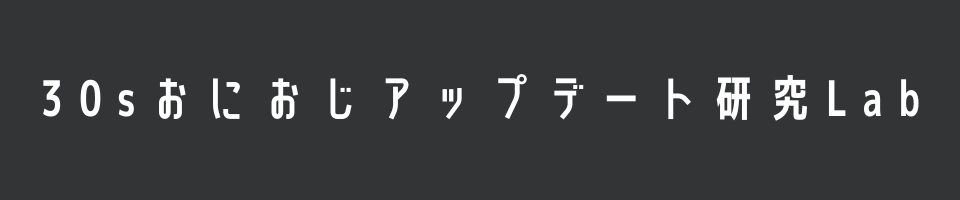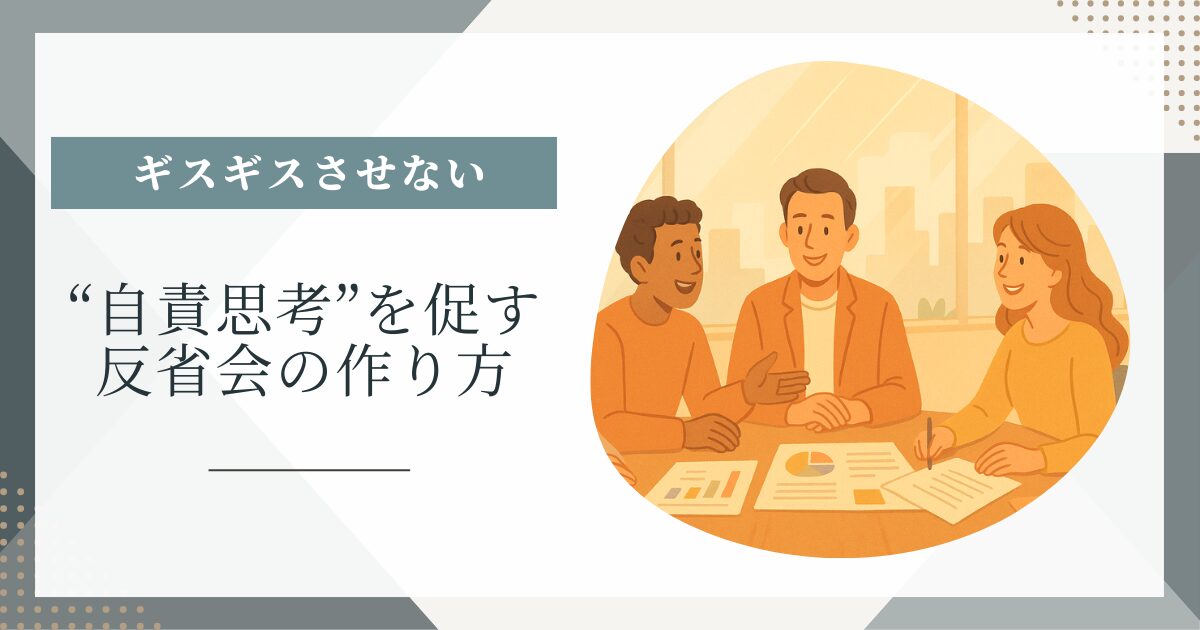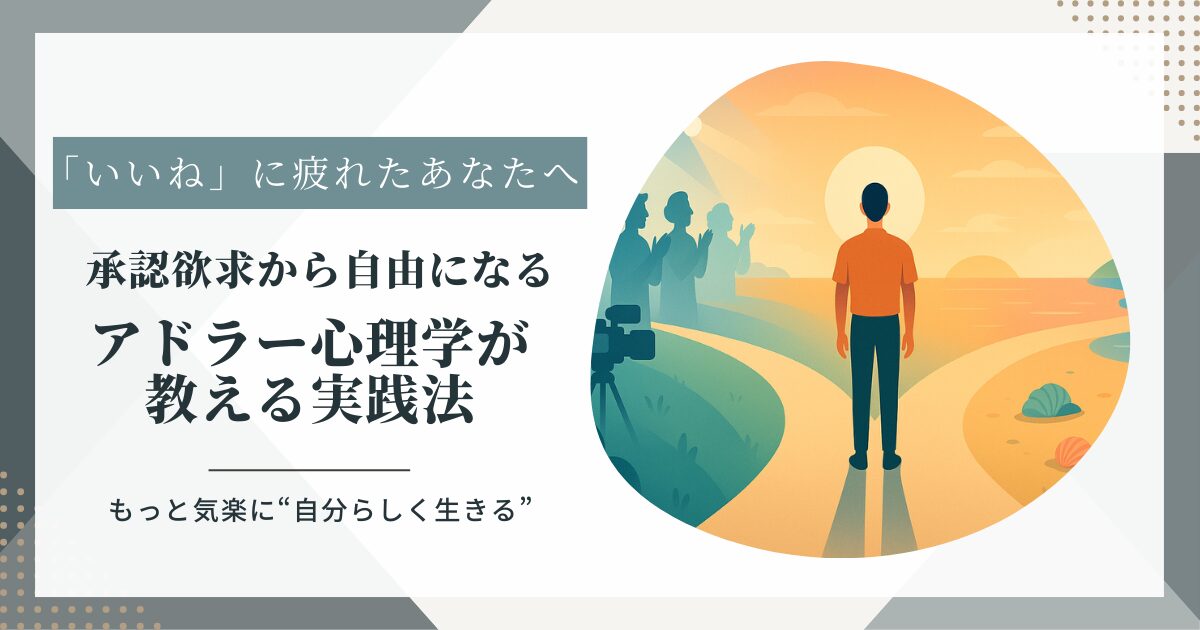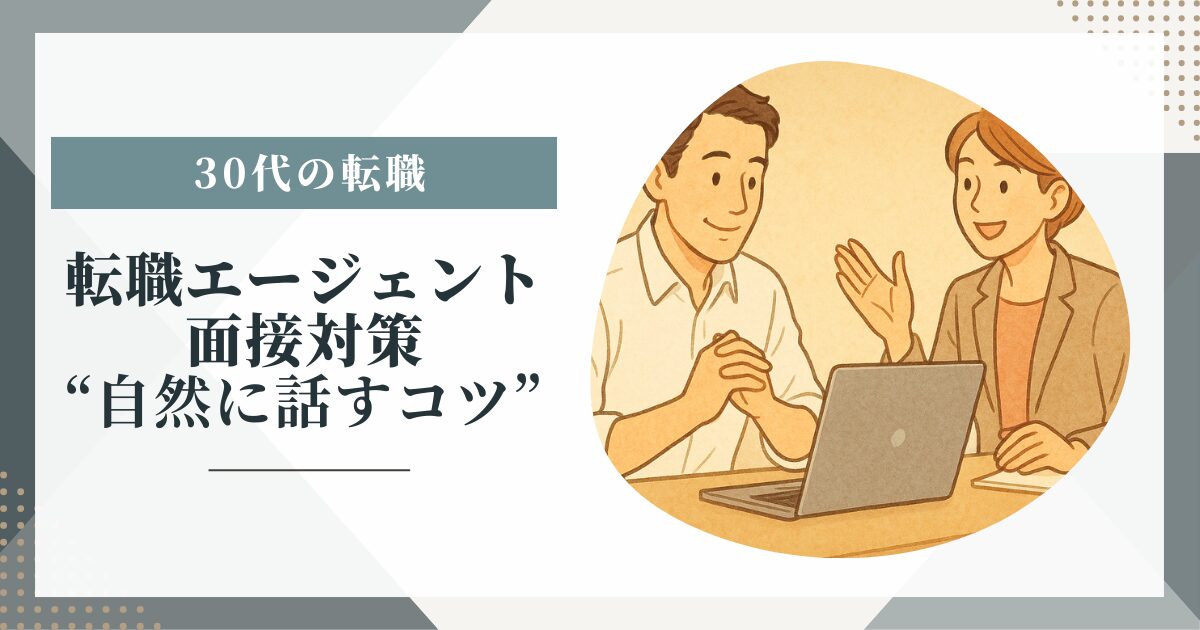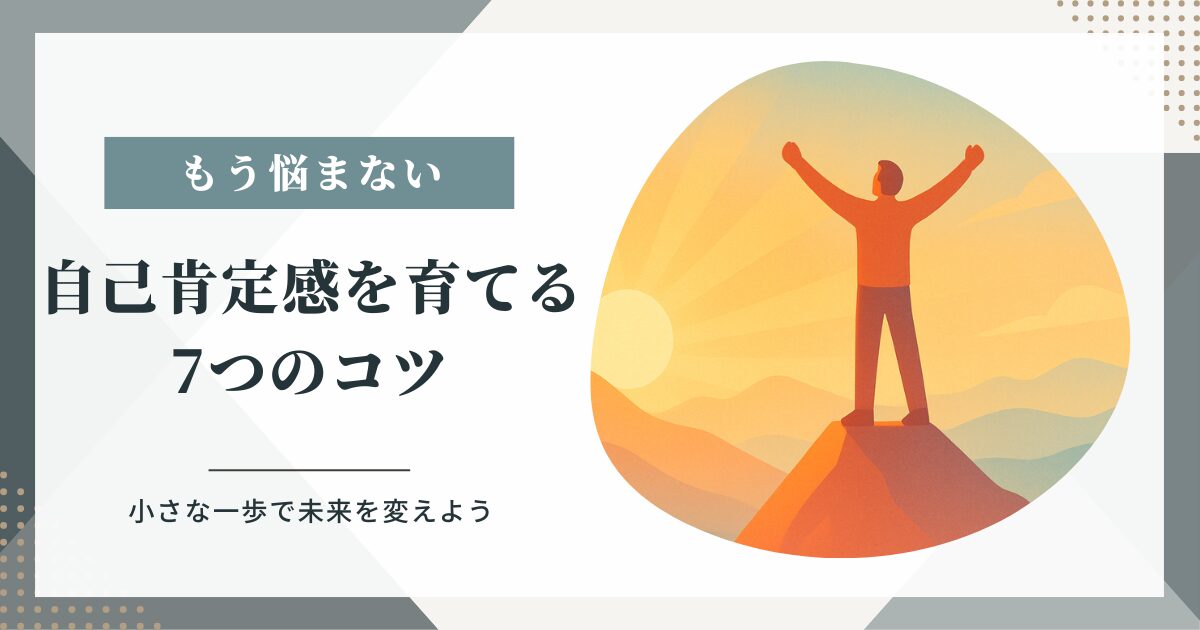5分で変わる!『書く習慣』書評と実践法【30代でも続く書き方】
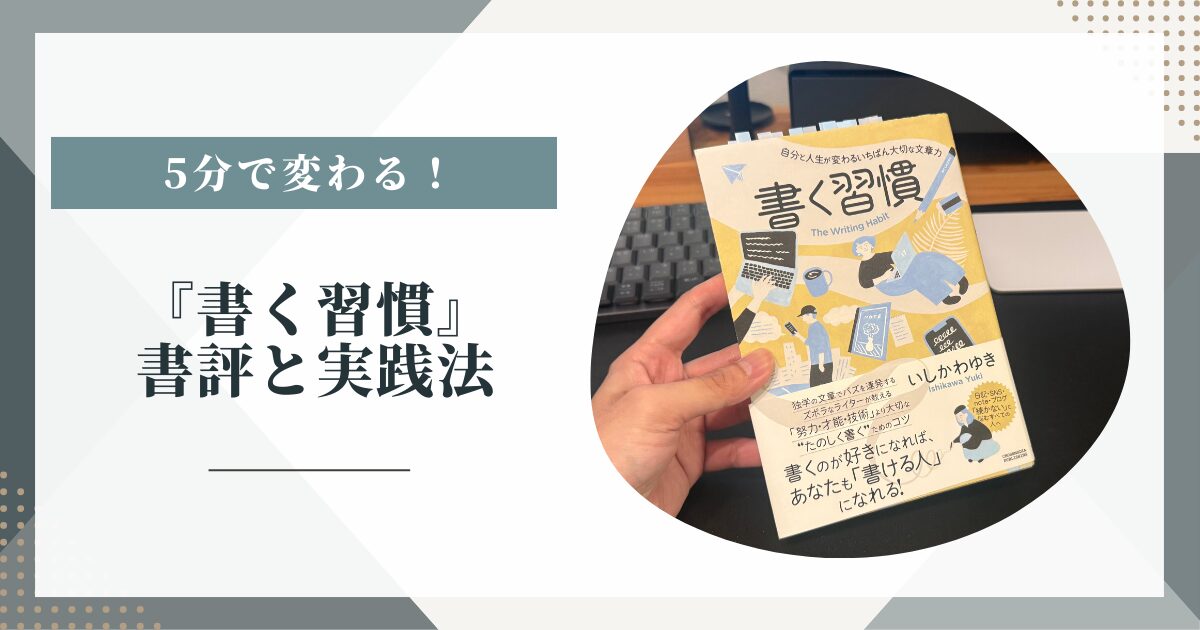
副業やスキルアップのために「ブログを始めよう!」と思ったのに、なかなか続かない…
SNSで発信しようとしても、完璧を求めて手が止まってしまう…
そんな経験、みなさんにもありませんか?
ぼく自身も以前は
「文章を書き続けるなんてとんだ苦行だよ!」
「ライティングの副業なんてできないよ!」
なんて思っていました。
でも、いしかわゆきさんの『書く習慣』を読んでから考え方が変わりました。
誰でもマネできるシンプルな方法で、文章を書くことは習慣化することができます!
そして、文章の発信は、自己表現だけにとどまりません。
収入アップや新しいキャリアにもつなげる事ができます!
この記事では、『書く習慣』の要点と、ぼく自身が得た学びをもとに、30代サラリーマンが今日から実践できる“書く習慣”の方法を紹介します。
この記事を読んでもらえれば、今日から”書く習慣”を身に着けて、ブログやライティングの副業を続けられるようになります!
『書く習慣』が教えてくれること
まえがきでもいいましたが、ぼくは、文章を書くことを“苦行”みたいに感じていました。
「才能ないから無理」「いい文章なんて書けない」と思い込んで、最初の一歩ですら全然踏み出せず…
でも、『書く習慣』を読んでみて「書くことは才能じゃなくて習慣なんだ」と気づくことができました。
習慣にできれば、書くことは苦行じゃなくなるし、書き続けることができれば、ぼくたちは人生を変える力を持てるようになります。
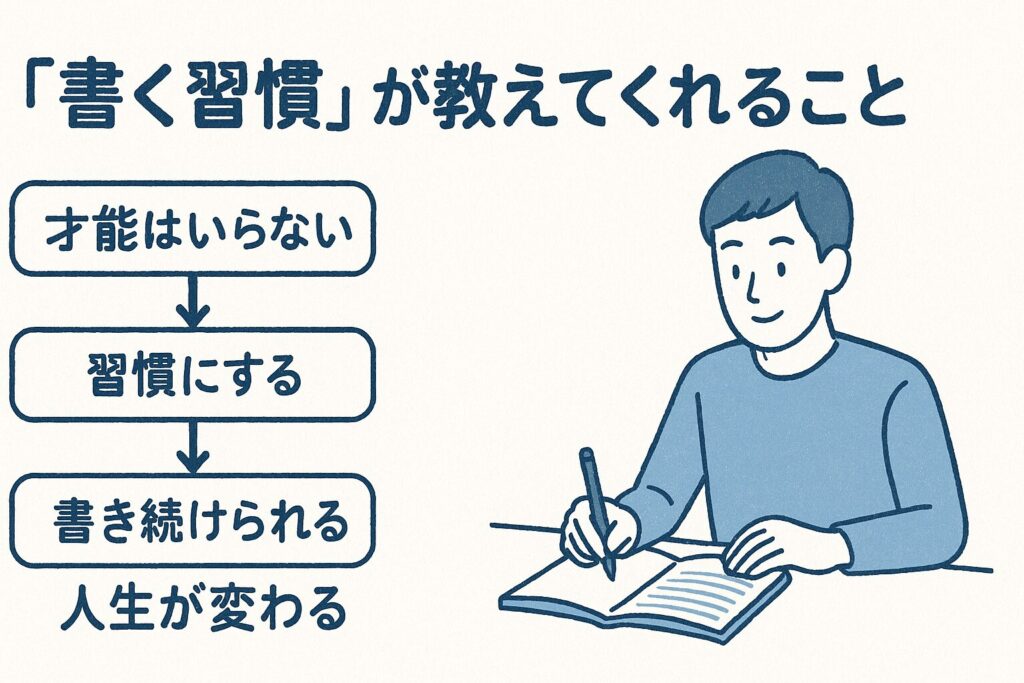
まずは自分のために書いていい
このフレーズを見た時、「これなら書き続けられるかもしれない!」と気持ちがすごく軽くなりました。
誰かに見せる前提で書くと、どうしてもカッコつけたり、余計なことを考えてしまいますよね。
だからこそ、最初は自分だけの日記のつもりで書いていい。
「うわぁ〜疲れた!」「今日のランチ美味しかった!」みたいな小さな本音を残すだけで、立派な文章。
そうやって最初は、文章を書くことに慣れていくことが肝心です。
大事なのは “言葉と仲良くなること”
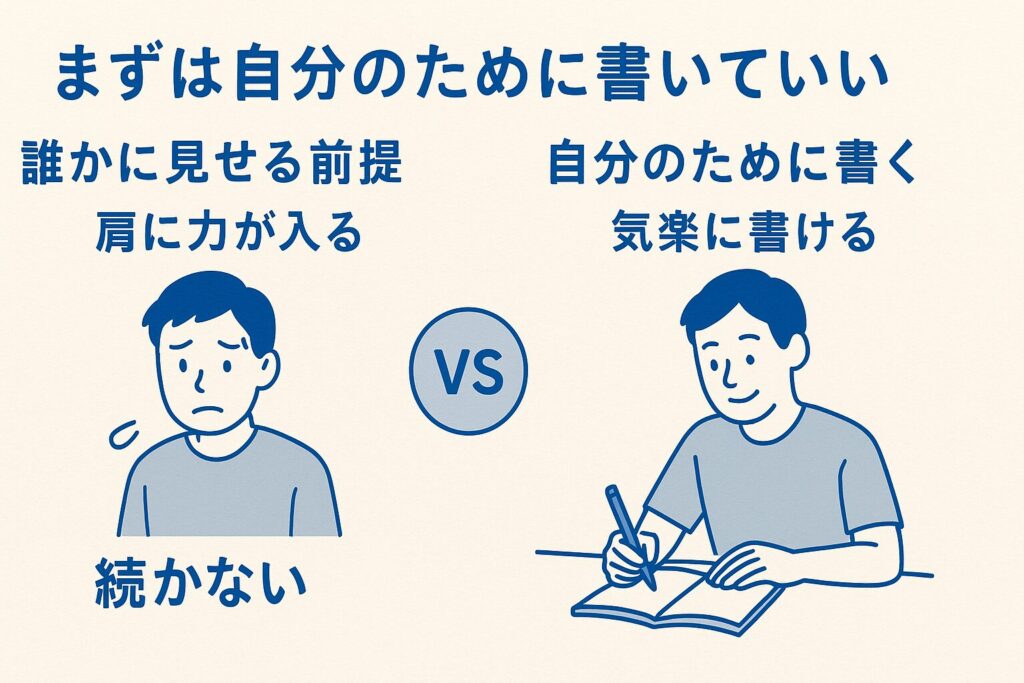
本の中では
自分は忘れるアホだから、書かないとダメ!
と自分に言い聞かせる方法も紹介されていて、目からウロコでした。
これってすごく合理的な考え方ですよね!
ぼく自身「絶対忘れるから書かなきゃ」というマイルールを設定したら、書くことが続けやすくなりました。
書くことを「才能の問題」ではなく「生活の一部」として捉えるだけで、ぐっと気持ちがラクになります。
まとめ
- 才能ではなく、習慣として書くことを生活に落とし込むのが大切
- 書くことは人生を変える力を持っている
- 最初は「自分のため」に書くことから始めればいい
書く習慣を無理なく続けるコツ
モチベーションが高まって「よし、書こう!」と思っても、続かなくて挫折…
これもあるあるですよね。
ぼくもそうで、2024年の12月から1ヶ月間、noteの執筆にチャレンジしていたのですが、
資格勉強を理由にしたり、SNSを開いたり、ゲームに逃げたり…
結局、”何も書けない””進められない”現実から、自己嫌悪を感じて活動をやめてしまいました。
そんなぼくでも今はこうして、ブログをはじめてから、1ヶ月以上休むことなく継続して執筆活動を続けられています。
『書く習慣』で紹介されている方法の中で、一番印象に残ったのは 「5分だけやってみる」 という考え方です。
人は「やる気があるから行動する」んじゃなくて、「行動するからやる気が出る」んですよね。
最初から長い文章を書こうとすると挫折しやすくなります。
「5分だけ!」と決めて、自分へのハードルを下げてあげると、「ちょっとくらいなら」と思って、自然と続けられるようになります。
やった事実が、自分への自信にもなるので、この効果は侮れません!
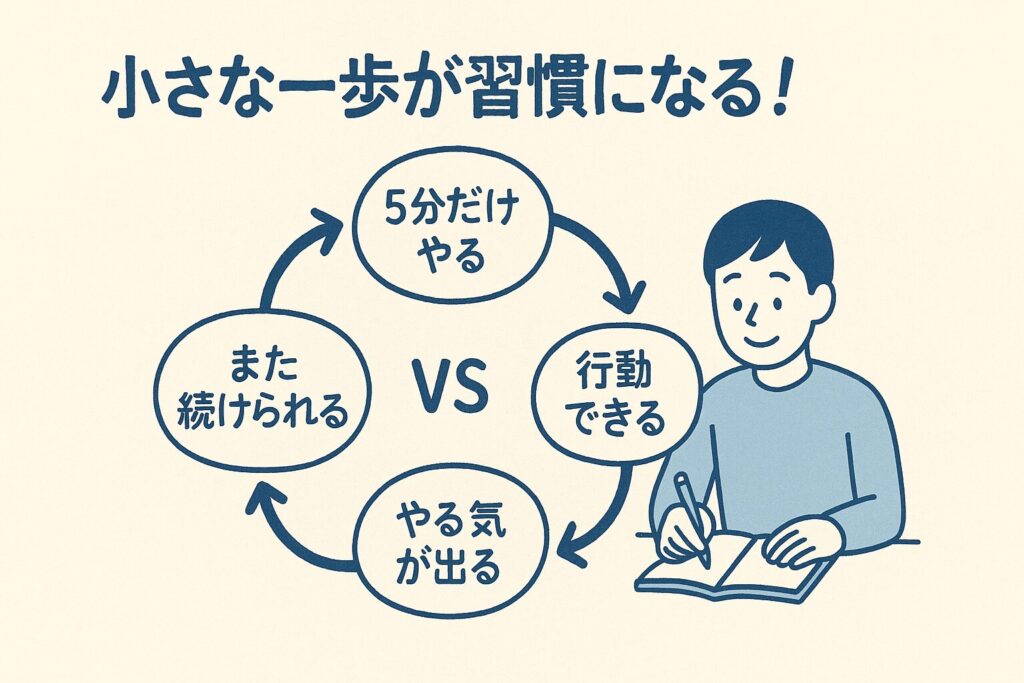
さらに、書くためのツールを目に見える場所に置いておくのも効果的です。
- 手元にノートとペンを置く
- スマホにメモアプリを常に開いておく
それだけで”書く”ことがぐっと身近になってきます。
ぼくも仕事中、プライベートどちらも欠かさず”ほぼ日手帳”を持ち歩くようにしてます。
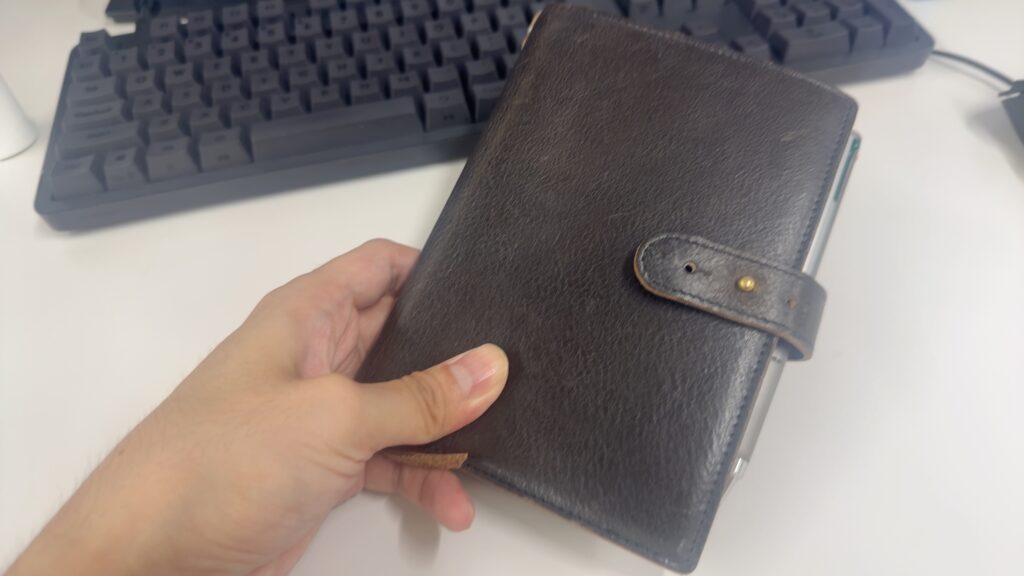
SNS投稿もおすすめされています。
とくにTwitter(現X)は無料登録で140文字しか書けないので、要点をまとめる練習にピッタリ。
「映画を見た → 感想を一言つぶやく」くらいの手軽さで、アウトプットの習慣をつけることができます。
あと、ても大事なことは、完璧を目指さないこと。
「文章として意味がないかも…」と考えてしまうと手が止まってしまいますけど、意味づけをしてくれるのは、読んでくれる読者です。
とりあえず書いて公開する。
この一歩が習慣化につながります。
まとめ
- 「5分だけやってみる」でハードルを下げる
- ノートやアプリを身近に置き、書きやすい環境を作る
- SNS・日記を活用してアウトプットの練習をする
- 完璧を求めずに、とりあえず公開してみる
ネタは日常にあふれている
「ブログのネタがない…」
「投稿のネタがない…」
そんな悩みから解放されたいですよね。
ぼくも最初の頃は「記事を書こう」ってパソコンの前に座っても、真っ白な画面を見つめながら、うんうん唸るだけで時間が過ぎていってました。
でも、『書く習慣』はそんな悩みも解決。
”ネタは探さなくても、日常にいくらでも転がっている”ってことを教えてくれます。
たとえば、
- コンビニで新しいスイーツを食べた感想
- 通勤中に読んだ本からの気づき
- 仕事で失敗した経験
- 「あ〜疲れた」みたいな小さな気持ち
こういう日常の一コマも、誰かにとっては「非日常」になります。
さらに、「好きなものを書く」と文章に熱量がのって、自然と読者に伝わりやすくなります。
ぼくの場合は、収入アップやスキルアップの挑戦、読書や外見磨きがまさにそれです。
だからこのブログでも、そのリアルな体験を中心に書いています!
どんな人も、「ネタがない」じゃなくて「気づいてないだけ」なんです。
普段の生活の中でアンテナを立てていれば、ちょっとした出来事も立派な記事のネタになります。
今日のあなたの当たり前の日常にも、きっと記事のネタが隠れているはずです。
まとめ
- ネタは探すものではなく、日常にあふれている
- 小さな体験や感情でも、他人にとっては価値がある
- 好きなことを書くと熱量が伝わりやすい
- 「ネタがない」のではなく「気づけてないだけ」
読者に届く文章の書き方
「どうせ書くなら、ちゃんと読んでもらえる文章にしたい」
そう思う人も多いと思います。
でしたら、小手先のテクニックよりも “本音で書くこと” が一番大事です。
「きれいな文章にまとめなきゃ」と思って、無理やり背伸びした文章を書くと、なんか自分ぽさやがなくて機械的になっちゃいます。
自分で読んでても「これつまんないな…」と思ってしまったり。
『書く習慣』では、こうアドバイスされています。
- 中学生でもわかる言葉で書く
- 身近な人や「昔の自分」に向けて書く
- 本音を隠さずに出す
これを意識すると、スッと頭に入ってくる文章になります。
変にカッコつけていないから、自然と読みやすくなるし、共感もしやすい!
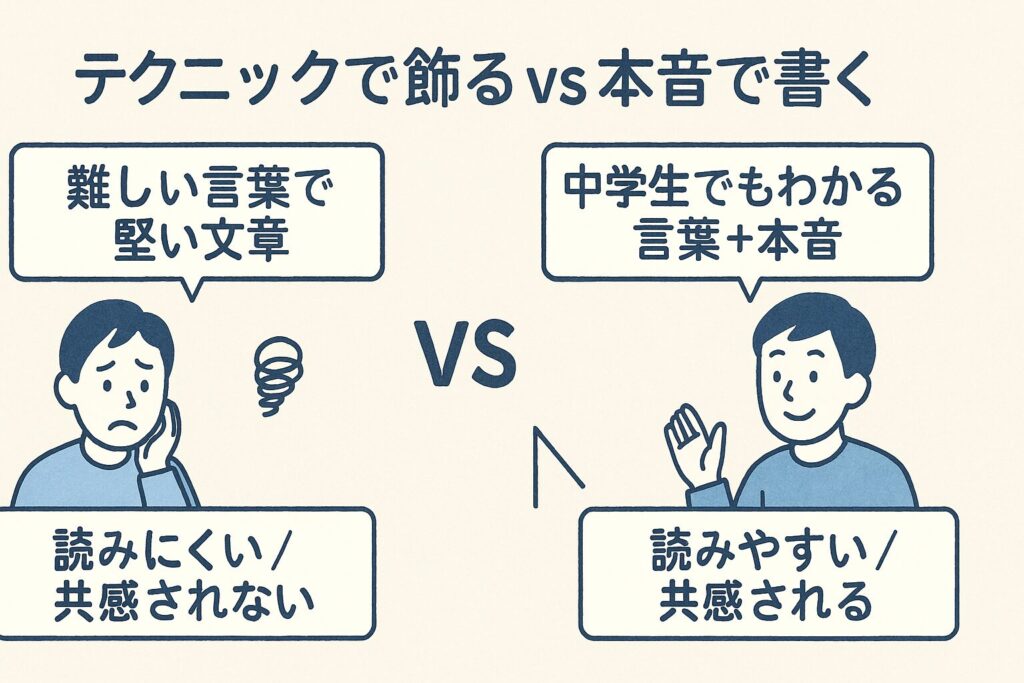
なかでも、「昔の自分に向けて書く」については、ターゲットがはっきりとイメージできるので効果的です!
ぼく自身、転職を怖がってた頃や、副業を始めた頃の不安を思い出しながら書くと、自然とリアルな表現や言葉が出てきます。
もし当時のぼくみたいに悩んでいる人が読んでくれたら、「あ、これ自分のことだ」って共感してくれやすくなるんじゃないかな、なんて考えています!
結局、読んでくれている人に届く文章は“うまい文章”じゃなくて“本音のこもった文章”なんです!
これはブログにもSNSにも共通して言えることだなと実感しています。
まとめ
- 本音で書くことが、読者に届く一番の方法
- 難しい言葉を避けて、中学生でもわかる表現にする
- 「昔の自分」や身近な人に向けて書くと共感されやすい
『書く習慣』を読んで得たぼくの変化
『書く習慣』を読む前のぼくは、文章を書くことなんてできないって考えてました。
「才能がないから無理」
「文章力がない」
そんな風に考えていたから当然ですよね。
でも、この本を読んでから少しずつ考え方が変わって、文章を書くことが”苦行”から”日常の一部”にシフトできました。
実際に続けられるようなって、自分の気持ちや行動にも大きな変化が生まれています!
ここからは、ぼくが『書く習慣』を通して得られた変化を4つ紹介します。
変化① 書くことが”苦行”じゃなくなった
以前のぼくは、”文章を書く=いやいや取り組む課題”ってイメージでした。
「書かなきゃいけない」と思うほど気持ちが沈んじゃって、結局手をつけられない…
でも、この本にある「まずは自分のために書こう」という考えに出会ってから、書くことのハードルを一気に下げることができました。
最初は日記に「今日疲れた」と書くだけからはじめてみました。
それでも「書けた!」という達成感がが積み重なっていって、今では書くことを生活の一部にすることができています。
変化② 不安を整理できるようになった
頭の中でぐるぐる悩んでいるときって、なにもしないとモヤモヤが増えるだけですよね。
「不安を書けば、悩みが可視化される」とあるんですが、たしかに、文章にすると気持ちが客観視できて、「こうすればいいかも!」と解決の糸口がみつかるようになります。
今では、「悩んだら書く」ことが自然にできるようになって、気持ちを整理するときにすごく役立っています。
変化③ 日常にネタを見つけられるようになった
以前は「ネタがない…」と悩んで、パソコンの前で固まってしまうこともしょっちゅうありました。
でも、「日常の一コマも誰かにとっては非日常」という考えを知ってから、考え方がガラッと変わりました。
普段の日常、読んだ本の一文、ちょっとした失敗
どれも書いてみると立派なネタになることがわかってきます!
今では、「ネタは探すんじゃなくて、気づくもの」ということがわかったので、日常が常にインプットです!
変化④ 本音で書けるようになった
昔のぼくは
「文章はきれいにまとめなきゃ」
「ちゃんとした文法を使わなきゃ」
と力みすぎて、すごくよそよそしい文章になっていました。
自分でも「これつまんな…」と思うくらい。
でも
「誰にでも書ける文章じゃなくて、自分の本音を出そう」
「昔の自分に向けて書けばいい」
この考え方に出会ったとき、無駄な肩の力が抜けました!
転職活動に踏み出す前の不安だったり、副業を始めるのが怖かった頃の気持ち。
そういうリアルな体験や思いを思い出しながら書くと、自然に言葉があふれてくるようになります!
そのおかげで記事に“自分らしさ”が出てきて、「文章を書くって楽しい!」と思えるようになりました!
今日からできる“書く習慣”アクション3つ
「習慣にするのが大事なのはわかったけど、結局どう始めればいいの?」
そう思われる方も多いと思います。
でも大丈夫です!
『書く習慣』で紹介されていた方法の中から、ぼく自身が実際に取り入れて効果があった“3つのアクション”を紹介します。
アクション① 「5分だけやってみる」
いきなり
「長文を書こう」
「1日1記事」
なんて意気込むと、ほぼ確実に挫折します!
だから最初は「5分だけ」と決めて机に向かいましょう。
たとえ数行の日記でもOKです。
「できた」という体験を積み重ねることが、最初はとても重要です。
積み重ねられるようになれば、自然と続けられるようになります。
続けるのが楽しくなったら、書く時間を増やしていったらいいんです。
アクション② 書く環境を身近に置く
書こうと思った瞬間にペンやスマホを手に取れるかどうかで、習慣化のしやすさが変わってきます。
- 手元にノートとペンを常備する
- スマホのメモアプリをホーム画面に置く
- SNS(Xなど)をアウトプット専用に使う
すぐ書ける環境が整っていれば「よし、書こう!」と気合を入れなくても、習慣化できるようになります。
アクション③ 本音をそのまま書く
「意味がある文章じゃないとダメ」と思うと手が止まってしまいます。
文章に対して意味付けをしてくれるのは”読者”です。
「今日疲れた」でもいいし、「上司にイラッとした」でもいいです。
まずは自分の気持ちをそのまま言葉にしてしまいましょう。
その一歩が、読者に届くリアルな文章に繋がっていきます。
まとめ
- 5分だけ書いてハードルを下げる
- 書く環境をつくって即行動できるようにする
- 本音を書いて言葉と仲良くなる
たったこれだけで、“書く習慣”は今日からでも、今からでも始められます。
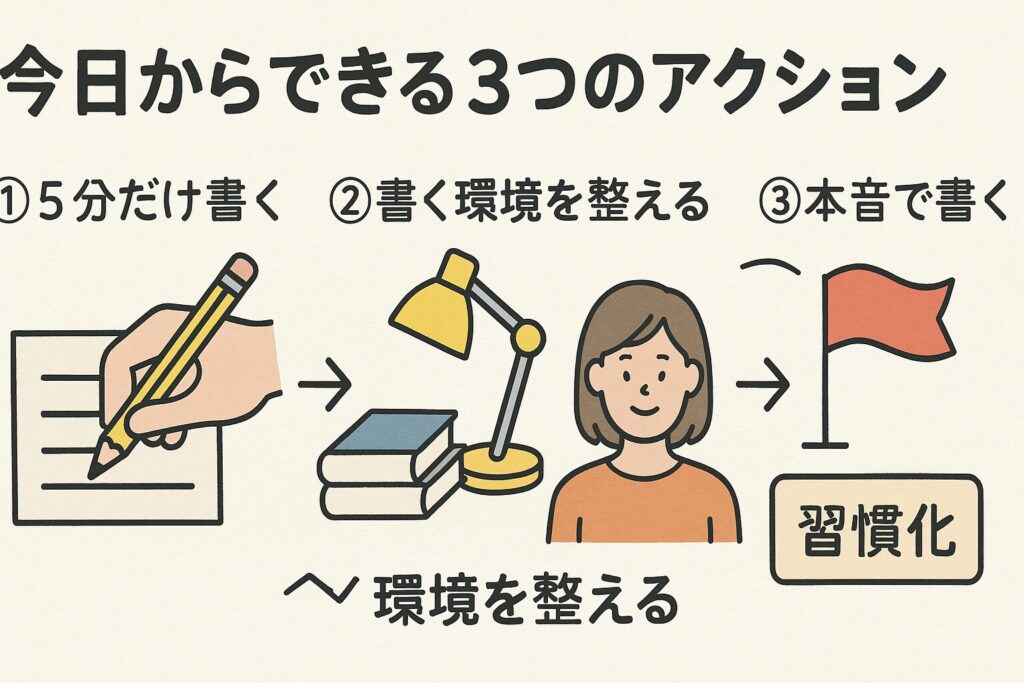
まとめ|今日から“書く習慣”を始めよう
いしかわゆきさんの『書く習慣』は、「書くことは才能じゃなくて習慣だ」と教えてくれる本です。
ぼく自身、この本に出会ったことで”文章を書くのは苦行だ”という思い込みがなくなって、毎日自然と書けるようになりました。
今日からできることはすごくシンプルです。
- まずは 5分だけ書いてみる
- すぐに書ける環境 を整える
- 本音をそのまま言葉にする
この3つを意識するだけで、書くことがぐっと身近になります。
「うまく書かなきゃ」なんて思わなくても大丈夫です!
あなたの日常の一コマや気持ちを言葉にするだけで、それは立派な文章になります。
あなたも今日から “書く習慣” を始めてみませんか?
未来のあなたが、きっとその一歩に感謝してくれるはずです!
それでは
あなたにいい明日がありますように!